令和6年度個人住民税の定額減税について
令和6年度の個人住民税について、定額減税(特別税額控除)を実施します。
所得税の定額減税については下記リンクをご覧ください。
減税額
納税義務者の所得割額から以下の合計額を控除します。
ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
本人:1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
(例)本人、控除対象配偶者、子2人の4人家族の場合
10,000円×4人(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)=40,000円
適用条件
納税義務者の令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。
※以下に該当する方は対象外です。
・個人住民税が非課税
・個人住民税均等割と森林環境税(国税)のみの課税の方
合計所得金額とは…配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等)などの総合所得を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。(特別控除適用前の所得金額で計算します。)
定額減税の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※ 定額減税が適用されない方は,通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等から差し引かれる市・県民税の額から定額減税を行います。控除しきれない場合は、12月分以降順次控除します。
※ただし、令和6年度の個人住民税において、初めて公的年金等に係る所得から特別徴収される場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、年度途中の税額変更等により公的年金からの特別徴収が途中で停止してしまった場合は、令和6年4月~8月分は公的年金からの特別徴収ではなく、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)の普通徴収として納付書が届きます。
上記の場合は普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の税額から順に控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月の公的年金からの特別徴収税額から控除します。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から定額減税を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
減税額の確認方法
納税義務者宛の各種通知書にてご確認いただけます。
(1)給与所得に係る特別徴収の場合(事業所に発送済)
令和6年度市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)
(2)普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月7日発送)
令和6年度市民税・県民税・森林環境税 納税通知書
定額減税・給付金詐欺を装った詐欺にご注意ください
定額減税については、国税庁や都道府県、市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。お心あたりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
その他
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税(特別税額控除)前の所得割額で計算を行うため、定額減税(特別税額控除)の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)




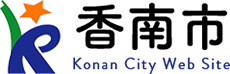
更新日:2025年08月01日